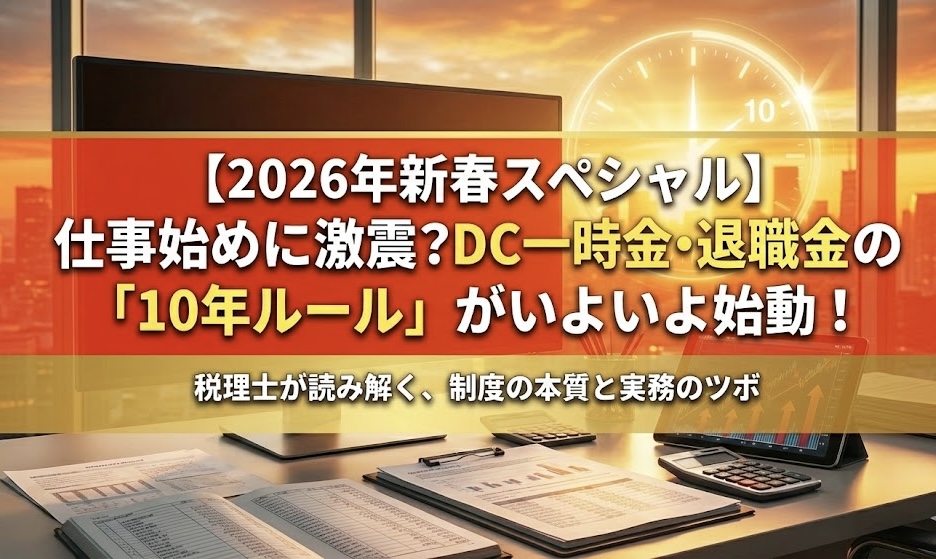「亡くなった父が、実は遠方に土地を持っていたかもしれない……」 そんな不安や手間が、今日から劇的に解消されるかもしれません。
本日、2026年・令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されました。これまでは各自治体を回って「名寄帳」を集めることが多かった不動産調査が、ついに「法務局での全国一括検索」という新時代に突入します。
今回は、税理士の視点から、この制度が実務や私たちの生活にどう影響するのか、その本質を整理します。
1. 「点」から「面」へ。名寄帳との決定的な違い
これまで、被相続人の不動産を調べるには、心当たりのある各市役所へ「名寄帳(なよせちょう)」を請求しに行く必要がありました。
- これまでの限界: 「その自治体の中」にある不動産しか分からない。
- これからの常識: 法務局の窓口一つで、「日本全国」の所有不動産がリスト化される。
まさに、宝探しを「勘」に頼っていた時代から、GPSを導入したような大きな転換です。
2. なぜ今、この制度が必要なのか?
背景にあるのは、2024年・令和6年から始まった「相続登記の義務化」です。 「持っていることを知らない不動産」であっても、登記を放置すればペナルティ(過料)の対象になり得る今の時代、この制度は相続人にとっての強力な防衛手段となります。
- 隠れた「負動産」の発見: 遠方で固定資産税がかからず通知も来ないような不動産でも、登記さえあればリストに載ってきます。
- 把握漏れリスクの低減: 相続税の申告において、不動産の見落としは致命的。相続財産の把握漏れ対策としても機能します。
3. 【専門家の眼】ここに注意!「住所の壁」
非常に便利な制度ですが、実務家として見逃せないポイントあります。それが「登記簿上の住所」の問題です。
この制度は、法務局が「氏名」と「住所」でシステム検索を行うものです。 もし、被相続人が30年前に不動産を購入したきり住所変更登記をしておらず、その後数回引っ越しをして亡くなった場合、「亡くなった時の住所」で検索しても、古い住所のままの不動産はヒットしません。
ポイント: 漏れをなくすには、戸籍の附票などで過去の住所履歴を遡り、「かつて住んでいた全ての住所」を条件に入れて検索するのが、上手な活用術です。
結び:相続を「霧の中」で終わらせないために
本日始まったこの制度は、相続という複雑なプロセスに「透明性」をもたらす大きな一歩です。
「どこかに土地がある気がするけれど、調べようがない」 そんな理由で手続きを止めていた方は、ぜひ一度、最寄りの法務局で相談してみてください。